
昨年度授業風景
2013年10月14日(月) 日本舞踊

男踊りの「寿」を習いました。
股をわったりと女踊りとは違う難しさです。

体と扇子を使っての表現です。
2013年9月28日(土) 長唄

今藤政太郎先生の長唄の講義です。
三味線を組み立てているところを見せていただきました。

2013年9月23日(月) 日本舞踊 西川鯉之祐先生、西川貴美子先生

『梅にも春』の稽古風景です。
美しい梅を眺めているイメージを持って踊ります。

2013年9月2日(月)、4日(水)、7日(土)

まず人形の頭をとり、洋服を全て脱がせて裸にしました。
この状態から服を着せていく過程を学びます。
 まずは上半身から。
まずは上半身から。
糸の付け方など、教わることはたくさんあります。
自分で糸を付けていくことによって、人形の構造がよく理解できたのではないでしょうか。
2013年8月19日(水) 8月28日(水)
 2人3脚に挑戦。
2人3脚に挑戦。
人形の足が繋がれているのが分かりますか?
息を合わせて遣う稽古になります。
この後、4人5脚を、最後には13人の人形すべて繋いで前進しました。
 片足を上げた時に重心はどこにあるかの稽古です。
片足を上げた時に重心はどこにあるかの稽古です。
こうしたことを疎かにすると人形はとても不自然になってしまいます。
2013年8月3日(土) 8月24日(土)
8月3日と24日、特別講義の先陣をきって「古典の台詞」の授業が行われました。 授業を担当頂きますのは、歌舞伎俳優の澤村藤十郎先生。
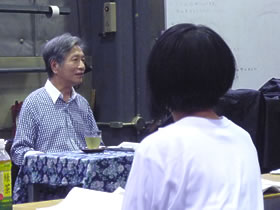 授業のテキストとしてお持ち頂いたのは「修善寺物語」。
授業のテキストとしてお持ち頂いたのは「修善寺物語」。
先生曰く、源氏の最期を、一時間弱の間に恋愛あり立ち回りありで岡本綺堂が見事に書き上げた作品。
作品を通して流れる「岡本綺堂節」を少しでも掴もうと、皆でいろんな役の台詞を声に出しました。
先生のお手本を聞き、登場人物の役どころや心情を伺って、初めての古典の台詞に戸惑いながらも、真剣に取り組みました。
 また台詞の他に、いかに稽古を重ねることが大切かということを伺いました。
また台詞の他に、いかに稽古を重ねることが大切かということを伺いました。
「稽古するしかない」という先生の言葉が印象的でしたね。
藤十郎先生、本当にありがとうございました。
2013年7月27日(土)

人形を持たずに、腰の位置を変えないよう歩く稽古をしました。
人形遣いの腰が上下したり、左右に振れてしまうと遣っている人形に大きく影響します。

初めて人形を前進させた時の様子です。
とっても覚束ないですが、今はもっと皆さん慣れてきました。
2013年7月13日(土) 開講式

人形の解説を皆で聞いているところです。
間近で人形を観て、皆さんが真剣に話を聞いくださるので講師も力が入ります。

初めて人形を手にしたところです。
はじめは基本姿勢をしっかり身体に覚えさせます。
人形をしっかり立たせるのは、思った以上に大変なことです。
人形に動きがついてくるのが楽しみですね。
